建売住宅大手の飯田グループホールディングスだけで、年間約4万戸の建売住宅を作っています。
当然、その中には当たりもあれば、ハズレもあります。
何万人という大工や職人が家を建てているわけですから、腕の差が出てしまうのです。また、腕が良い職人であっても、納期に追われて作った家は、クオリティが下がってしまう事があります。
建売住宅の中には、雑な仕事で作られた「買ってはいけない物件」が混じっているという点には注意してください。
しかしそんな物件を避けることができたら、建売住宅はコスパがよく、「納得できる家」になるはずです。
「マイホームを買う」というのは人生の一大事業ですから、着実なステップで「ここなら買ってもいい」という家を探しましょう。
この記事では、自ら建売住宅を企画して販売した経験を持つ筆者が、「こんな建売住宅は買うな」と言われる物件の要注意ポイントと、わかりやすいチェック方法を解説します。
この記事は宅建士資格を保有するアップライト合同会社の立石秀彦が制作しました。
「こんな建売住宅は買うな」といわれる物件とは?

建売住宅は良くも悪くも、たくさん作ることでコストを落とし、同じ仕様の建物を安く販売するという商品です。
たくさん作ることでコストダウンがはかれますから、画一的な内・外観となることは、一定程度しかたのないことです。
ただ、問題なのは「大工さんや職人さんの当たり外れによるクオリティの差」です。
たくさんの住宅を作らないといけないので、常に人手不足が続いており、どうしても経験が浅い大工が担当する家も出てきます。
腕の悪い大工が施工した建売住宅は、確かに「買うな」といわれても仕方がない場合があります。建売住宅購入時には、こういった物件を見分ける知識が必要になります。
八王子市を中心とする多摩地区であれば、クラシエステート株式会社の溝口社長が、建売住宅購入を無料サポートしています。不安な場合はご相談ください。
お問い合わせフォーム|クラシエステート株式会社
サポートはすべて無料ですし、相談ベースでもかまいません。
「買うべきでない物件」が作られてしまう理由

建売住宅は大量に作られていますが、自動車や家電製品のように工場で作ることができません。現場で建築する必要があります。
そこで、どうしても現場によるレベル差が生まれてしまう…というのが「買うべきでない物件」が作られてしまう理由だといえるでしょう。
理由① 価格優先で合理化しすぎている
建売住宅を安く供給するために、どのメーカーも大量仕入れにより材料費を抑え、また工期を短縮することで価格を圧縮しています。
一般に注文住宅であれば着工してから半年から1年程度かけて建築しますが、建売住宅の場合は1~2か月で完成します。
例えば、某ハウスメーカーでは毎年契約工務店を集めて「いかに早く住宅を建てられるか」というコンテストを行っています。優勝チームは建て方が始まってから「3日で完成する」といわれており、驚くほどの短納期を実現できることがわかります。
このように工期を短縮し、合理化すること自体はいいのですが、合理化の裏で慌ただしく工事が進み、工程をひとつ飛ばしてしまったり、雑な施工になってしまう可能性があります。
現場によってはそのしわ寄せで、建物のクオリティに疑問符がついてしまいます。
理由② 大工・職人が足りず新人まで動員している
知り合いの大工さんが「しょっちゅう建売住宅の現場に誘われて困る」とボヤいています。パワービルダーの建売の現場はいつも人手不足なのです。
そのため、中には経験の浅い大工さんが混じっていることもあります。こういう人が建てた物件に当たってしまうと、クオリティ的に粗が目立つのは当然でしょう。
完成後に見える部分ならいいのですが、建築している途中のミスは、後から見てもわかりません。判断が難しく、経験のある不動産会社や建築士などでないと不具合を見抜けない可能性があります。
理由③ 現場監督が多数の現場を抱えすぎていて目が届かない
筆者は以前、建売住宅の建築現場で大工さんに「現場監督はどれぐらいの頻度で来ますか」と聞いてみたことがあります。その時「ここ2週間ほど見ていない」と言われて驚きました。
2か月程度の工期のうち2週間空けているということは、めったに現場を見ていないということです。
本来であれば未熟な大工の仕事をしっかり監督すべき大手ハウスメーカーの現場監督は、忙しすぎてなかなか現場をまわれていません。
そこでますます大工の腕の差が出てしまうことになります。
経験豊富な大工であれば、自分たちの判断でミスが出ないように進めることができるものの、経験の浅い大工は重大なポイントを見逃してしまう可能性もあります。
「現場任せ」に近い状況になっているのです。
もちろん、買い求めやすい価格帯の建売住宅であっても、設計通りにきちんと建てられていれば、長く住める問題のない住宅だといえます。
しかし、合理化を推し進めた上に人手不足が重なることで、中には「こんな建売住宅は買うな」といわれる物件が存在するのが実情です。
では、そんなハズレ物件をどうやって見分ければいいのでしょうか? それが次章のテーマです。
「買うべきでない建売住宅」13のチェックリスト

建売住宅メーカーの営業マンと一緒に建物を見学すると、すぐ建物内に通されます。しかし筆者はまずは建物の外観から見たほうがいいと考えています。
外から排水経路、日当たりなどの概要を見たうえで、建物外観に問題がないかを確認します。
外観編
建物を外側から見学する場合、周辺環境も含めてチェックしておいてください。日当たりや風通し、騒音、ゴミ捨て場の位置、電線の位置や電波塔の有無などは、まず確認しておきたいポイントです。
そのうえで、建物敷地内では、以下の点について順番にチェックしていきます。
敷地にタバコの吸い殻やゴミが散乱していないか?
筆者が見たハズレ物件の現場で印象に残っているのは、庭の隅にタバコの吸い殻がまとめて捨てられていたり、細かい木屑が散乱していたケースです。この現場では、外装工事の担当者の腕が悪く、外装の仕上がりに難がありました。
やる気のない職人の現場は、どこかだらしないものです。また、大工が道具や資材を整理整頓できていない現場では、大工の腕が悪い傾向があります。
腕の良い職人さんは、どんなジャンルの職人さんであれ現場をきれいに片付けてから帰っていきます。現場がきれいかどうかということは、職人さんのレベルを測るひとつのバロメーターになります。
ドア・窓枠などに小さな凹みや傷がないか?
これもゴミと同じく「職人さんのバロメーター」になるのですが、アルミ製の勝手口ドアや窓枠などに細かい傷がちょこちょことついているといったケースがあります。
外壁のサイディング(窯業系サイディング)に、何かをぶつけたような細かい傷が目立つ物件もあります。
こういった現場でも、大工さんや職人さんの意識が低く、雑な仕事がされている可能性があります。
もし細かい傷等が目についた物件があれば、その他の問題点についても厳しく見ておいた方がいいでしょう。
外装のコーキングに切れがないか?見切りはきれいか?
コーキングとは、サイディングとサイディングの隙間や窓の周りのすき間を埋めている樹脂製の詰め物です。
一般に、外壁のサイディングを貼る職人さんとコーキングを打つ職人さんは別のケースが多く、コーキングはプロが施工しているはずです。
意識の高いコーキング職人さんは、仕事に誇りを持っており、市販されているコーキングヘラという道具をあえて自分で納得のいく形状に作り、それを使っていたりします。
こういった意識の高いコーキング職人さんが施工した現場なら良いのですが、中には見習いの職人が施工したり、ピンチヒッターで大工さんが施工したりといったケースもあります。
コーキングが切れてしまうと、そこから建物内部に雨水などが浸透し、建物劣化の原因になります。そこでコーキングに切れ等がないかチェックしてみてください。
一般に一見してきれいなコーキングを打つ職人さんであれば、そのようなミスはあまりないでしょう。
雨樋が垂直に取り付けられているか?
屋根は登らないと見えないのですが、屋根職人さんが施工することが多い雨どいに関しては、外からすぐにチェックすることができます。壁に対して平行に取り付けられているかどうかを確認してみて下さい。また軽く手で揺すってみて、金具に緩みがないかどうかもチェックします。
実は雨どいに問題があるケースは少なく、万が一雨どいに問題がある場合は、かなり職人さんの腕が気になる兆候だといえます。
外壁にカビや黒ずみが目立つ部分がないか?
施工が悪いと大雨が降ったときに、屋根の1カ所から強い勢いで水が吹き出してきたり、雨どいに水たまりが残ってしまうことがあります。そのような場合まだ新しい家なのに、外壁の一部にカビや黒ずみが目立つということもあります。
念のため家の周りをぐるりと回ってみて、目立つ黒ずみなどがないかを確認しておきましょう。
室内編
室内を確認するとき、筆者はあえてスリッパを履かずに靴下一枚で歩くようにしています。床に鳴りやきしみがないかをチェックするとき、ダイレクトに感覚がつかめるからです。
また、最初に床、特に各部屋の四隅を見て違和感がないことを確認しています。床と壁の継ぎ目を隠すように配置されている巾木(はばき)の仕上げや、隅の仕上げがきれいかどうかはチェックポイントのひとつです。
その他、以下のような点をチェックしています。
キッチンや浴室のコーキングがきれいに打たれているか?
浴室など水回りの施工精度は建物の寿命に影響を与える可能性があります。
浴室が水を漏らさない性能を「水密性」といいますが、この水密性がきちんと性能通りに出ておらず、水が漏れてしまうような場合は問題です。床下に水が溜まり、湿気によって建物の寿命を縮めてしまうからです。
一般に浴室とキッチンは同じ設備屋さんが施工することが多いため、筆者はまずキッチンのコーキングなどの施工精度を見て、その職人さんがきちんと仕事をしているかどうかをチェックします。
その後浴室も確認しますが、なかなか浴室の水密性までチェックする事は難しく、仕上げがきれいかどうかといったポイントを見ていきます。
階段に隙間やずれがないか?
建物の構造部の木材はプレカットといって工場でカットされた状態で現場に搬入されます。大工さん自身が木材を切ることなく、プラモデルのように柱や梁を組み立てていくのですが、階段に関しては現場で木材をカットするケースがあります。
現場での木材加工は、大工さんの腕が現れるところ。階段を見てみて、隙間や水平垂直にズレがある場合は、大工さんに問題があるかもしれません。
もっとも階段であってもプレカットされて現場に搬入される場合も多いので、「階段の加工がきれいだから、大工さんの腕がいい」という逆の証明にはなりません。
床下にごみが放置されていないか?
フローリングの点検口や床下収納を開けてみて、床下の基礎の部分にゴミが残されているケースもあります。
大手の建売住宅ではかなり少ないですが、万が一床下の基礎部分にゴミが残っているような現場であれば、かなりモラルが低いといえるでしょう。こういった物件についてはより細かくチェックをし、問題があれば購入を見送った方がいいでしょう。
完成後の住宅の見学では内部構造を見ることができないので、職人さんのモラルから推測することになります。
床にビー玉やパチンコ玉を置いた時転がらないか?
建物が1000分の6以上傾いていると生活上も問題が生じるといわれています。そこで、床の傾きをチェックするためにビー玉かパチンコ玉を1つ持っていき、床に置いてみてください。ビー玉やパチンコは転がっていきますので、それで判定することができます。
建物の傾斜の許容範囲
| 1000分の3(約0.17度)未満 | ほとんどの人が傾斜を感じない。構造的な影響も軽微。 |
| 1000分の3~6(約0.17度~約0.34度) | 一部の人が傾斜を感じる。建具の開閉に不具合が生じ始めることがある。 |
| 1000分の6(約0.34度)以上 | 多くの人が傾斜を感じ、不快感を覚える。構造体への影響が懸念され、修繕が必要と判断されることが多い。 |
かつて筆者自身が企画した建売住宅が、ちょうど1000分の6ほど傾いていたという事件がありました。この時は弁護士に手伝ってもらい、土地を造成した土木会社と建築したハウスメーカーに建物を買い取ってもらいました。
そういった交渉は大変なので、床や柱の傾斜は必ずチェックしてください。
全ての窓や雨戸がスムーズに開閉できるか?
建物に歪みや傾きが生じると、窓やドアがスムーズに開閉できないことがあります。新築住宅の場合、まずめったにないのですが、中古住宅では窓が開きにくかったり、ドアの開閉時に引っかかりを感じることがよくあります。
筆者は新築であっても念のため全ての窓の開閉をしてみて、スムーズに開け閉めできるかをチェックしています。
場合によっては網戸がしっかり取り付けられておらず、開け閉めしただけで網戸が取れてしまった住宅もありました。こういった点をチェックするためにも、窓がスムーズに開閉できるかどうかを確認しておいてください。
室内に湿っぽかったりカビ臭い部分はないか?
建築時に大雨が降った場合、本来であればしっかり乾燥させてから建築を続けるのですが、工期が限られている建売住宅の場合、あまり乾燥をせず、基礎や根太が濡れたまま施工を続けるということもあります。
過去に筆者が経験した事例では、新築住宅の廊下の壁にカビが発生し、壁紙を2度貼り替えても改善しなかった例があります。
そういった施工がされた住宅の一部では、裸足で歩くと床が妙に冷たかったり、部屋の隅に湿気を感じることがあります。気をつけて見ておいてください。
建売住宅内覧時に持っていきたい7つ道具

筆者は建物をチェックするときに、以下のような道具を揃えていました。いつも小さな鞄に入れて自動車に積んでおくと、建物内覧時に便利に使うことができます。
ズーム付きのデジカメ
筆者は物件の内覧に行く時は必ずズームのついたコンパクトデジカメを持っていきます。スマホでも写真は撮れるのですが、望遠ズームがありません。しかし、コンデジの望遠ズームであれば、かなり遠くのものを大きく写すことができます。
例えば軒天に施工不良があるとか雨樋の施工状況をアップで見たいといった場合は、ズーム付きのデジカメが大変役に立ちます。望遠鏡でもいいのですが、デジカメであればそのまま現場写真を撮影することもでき、後々見返すことができます。
メモ帳とペン(あればふせんも)
複数の物件を1日で見学する場合などは、絶対にメモ帳とペンが必要です。例えば「大きくて使いやすいクローゼットはどの物件にあったんだっけ?」とわからなくなってしまうからです。
よかった点や気になった点をメモしておき、後々検討する時に資料として使えるように保管しましょう。
メモ帳はなくても物件概要書(物件資料)に書き込めば問題ありません。ただ、ペンはどうしても持っておきたい道具の1つです。
また、購入を前提として細かい不具合の修正内容を交渉していくような段階では、付箋やマスキングテープがあると便利です。気になるか所に貼り付けておき「ここです」とわかるようにしておきましょう。
小型の懐中電灯
物件の内覧時には電気が来ていないこともあるので、小型の懐中電灯を持っていくようにしてください。例えば、キッチンの戸棚の中や階段下の収納内部をしっかり見ようと思ったら、懐中電灯が必要になることがあります。
また、床下の点検口から内部を覗く場合にも懐中電灯があると便利です。
方位磁石(スマホアプリで代用も可能)
物件内覧中にどちらが北で、どちらが東で……と、部屋の窓が向いている方角が気になることがあります。
そこで不動産屋さんは方位磁石をポケットに入れています。最近ではスマホの方位磁石アプリで代用することができるので、スマホで対応してもいいでしょう。
水平器(ビー玉・パチンコ玉でもOK)
水平・垂直を確認するための水平器という道具はホームセンターなどで手に入ります。建売住宅を買う際に失敗しないよう、ぜひ用意しておいてください。
簡易的なものなら100円ショップでも手に入りますし、ホームセンターでも数百円から販売されています。
床が水平かどうかは、ビー玉やパチンコ玉を置いてみて「転がらない」ことで確認することもできます。
ただし、ビー玉やパチンコ玉では柱の垂直が確認できないので、水平器を持っていくのがベストです。
メジャー(できれば5m)
ある程度物件購入を前向きに検討する段階では、廊下の幅や冷蔵庫を置くスペースのサイズが気になってきます。そんな場合、小さなものでも良いので、メジャーを用意しておくと役に立ちます。
「手持ちのベッドが寝室に収まるかどうか」といった点も、メジャーがあれば確認できます。
この場合、できれば5m程度の長めのメジャーを用意しておくと、長さが足りずに困る事がなく便利です。
スマホ+おすすめスマホアプリ
実はメモ帳や懐中電灯、方位磁石などはスマートフォンで代用することも可能です。水平器も、水平器アプリを入れておけば、大雑把に水平・垂直を測ることができます。
なので、スマホひとつでもある程度の建物チェックは可能だといえるでしょう。さらに以下のようなアプリを入れておくと内覧時に活躍してくれます。
スマホ耐震アプリ「被害ナビ」
AndroidとiPhoneに対応し「スマホがあれば耐震診断ができる」という神アプリがあります。
東京理科大学の工学部建築学科高橋教授が開発したアプリケーションで、ものの数分で建物の簡易耐震診断が完了します。
もちろん厳密な計測ではなく、参考値に過ぎませんが、耐震性に問題がありそうな物件の場合、ポケットからスマホを取り出して、さっと耐震診断できる点は便利です。
被害ナビ|東京理科大学
Hazardon
iPhoneやiPadでハザードマップを閲覧できるHazardonというアプリもおすすめです。
使い方は簡単で、アプリを起動したら右上の「ハザードマップ」というボタンをタップし、見たい内容(「土砂災害警戒区域」など)をオンにするだけ。
設定画面を閉じると、地図上にハザードマップが表示され、その場でチェックすることができます。
大阪府箕面市にある株式会社アルカディアが制作している無料アプリで、広告も表示されず、快適に利用できます。
防災アプリHAZARDON|Arcadia
こんな建売住宅は買うな!地盤を確認する方法

この章では「自宅に帰ってきてから、今日見学した家の地盤が気になった」という場合に役立つ調査方法をお伝えします。
一番簡単でおすすめなのが今昔マップを利用する方法です。
今昔マップを利用して「昔その土地に何があったか」をチェック
その土地が昔、池や川や田んぼであった場合は地盤がゆるい可能性があります。そこで「その土地に昔何があったのか」という点を調べておくと安心材料になります。
その調査に使えるのが、埼玉大学教育学部の谷先生が作って公開している「今昔マップ on the web」というWebサービスです。
今昔マップon the Web|谷謙二研究室
これは現在の地理院地図と過去の古い地図を連動して比べられる便利なツールで、年代を遡り、「昔この土地が何だったのか」を確認できます。
より詳しい内容は筆者のブログで解説していますので、気になる方はそちらで確認してみてください。
気になる場合は土地登記簿を取得して過去の地目をチェック
土地の登記簿を取得するとその土地の過去の履歴が取得できることがあります。筆者の経験では、宅地の登記簿を取得して、かつては地目が「ため池」だったということがありました。
登記簿は民事法務協会のホームページから、オンラインで取得することができます。利用者登録しなくても「一時利用」を選べば、簡単に手続きができるので、一度試してみてください。
登記情報提供サービス|民事法務協会
登記簿で疑問点が残った場合は、コンピュータ化される以前の古い謄本である閉鎖謄本や移記閉鎖謄本を調べることもあります。その場合は、近くの法務局に足を運ぶ必要があります
閉鎖謄本では、明治時代まで遡り、かなり古い記録を調べることができます。ただし、こういった古い謄本や地図が残されているかどうかは、調べてみないとわかりません。
補足情報:現地で地盤を簡易調査する「親指テスト」とは?
気に入っている建物だけど「地盤が気になる」と悩んでしまうこともあります。最近は建築確認申請の際に地盤調査が義務づけられているので、よほどの事がない限り、十分な地耐力があるはずです。
しかし、現地で地盤について「違和感があるな」と感じる場合は、親指テストという簡易的な地盤の確認方法が使えます。
このテストでは、まず踏み固められて締まっている土地表面を避けるため、30センチほどの深さの穴を掘ります。
親指テスト
| 親指が土中にめり込む | 粗い(柔らかい)地層 |
| 跡が残る程度 | 中程度 |
| 跡もつかない | 密度の高い(固い)地層 |
もちろん、厳密な地耐力はわかりませんが、一定の参考になります。
おすすめ書籍「こんな建売住宅は買うな」
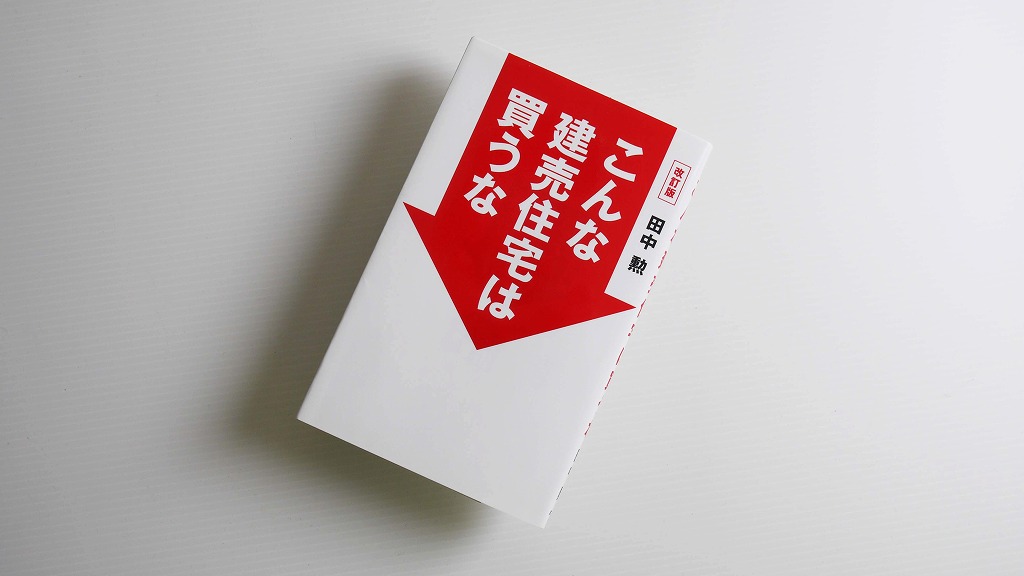
筆者は主に自分自身の経験に基づいて、この記事を書いています。
一方上記の「こんな建売住宅は買うな」という本の著者は、さらに多くの経験を積んできており、筆者とはまた違った観点で「買ってはいけない建売住宅の見分け方」を解説しています。
気になる方は、この本も読んでみてください。
筆者と意見が合う部分と全く違う観点で書いている部分の両方があるので、かなり参考になると思います。
まとめ「不安な場合はプロが無料サポート」

ここまで見てきたように「こんな建売住宅は買うな」といわれるケースがあるものの、建売住宅にはメリットもあります。メリットは安くて十分に品質の高い住宅を購入できることです。
安さを実現するために建売住宅メーカーは大量の住宅を建築し、工期を圧縮することでコストダウンを図っています。
問題は、そのしわ寄せで時にダメ物件がまじってしまうこと。
この記事では「買ってはいけない建売住宅を見分ける」という観点から、具体的なチェックポイントを13点に絞って解説してきました。
ただ、他にも見るべきポイントやチェックポイントはありますし、プロならではのカンや経験が必要なケースもあります。
そこで住宅購入が初めてだったり、不動産にあまり自信がないという方は、無料で利用できるプロの同行チェックサービスを利用してみてください。
クラシエステート株式会社では、宅建士資格を保有する担当者が無料で現場に同行し、買うべきか避けるべきかの判断をお手伝いします。エリアは八王子市を中心とした多摩地区に限られますが、建売住宅をご検討の方は、ぜひ一度ご相談ください。
お問い合わせフォーム|クラシエステート株式会社
仲介手数料は無料です。また、その他諸費用をいただくこともありません。