借地借家法は2022年5月に改正が施行され、電子契約の導入が可能となりました。この法律は、1921年に制定された旧法借地法を改正し、1992年に成立した現行法です。
現行の借地借家法は、借地人と地主の権利バランスを適正化することを目的として制定されました。
戦後の高度経済成長期には、土地の価値が急騰し、借地権の重要性が増大しました。都市部での人口集中により、土地の有効利用が社会課題となり、これまでの借地人を過度に保護する制度の見直しが求められたためです。
明治時代の封建的な土地制度から脱却し、近代的な民法体系が確立される中で、借地制度も大きく変化しました。1909年の「建物保護ニ関スル法律」から始まり、1921年の借地法・借家法の制定、戦時中の改正を経て、現在の借地借家法へと発展・継続しています。
旧法借地法の歴史的背景

旧法借地法は、1921年(大正10年)に制定され、借地人の権利を強力に保護する制度でした。この法律は、土地所有者と借地人の関係を法的に明確にし、借地人の地位を安定させることを主要な目的としていました。
戦後の昭和16年(1941年)改正では、戦時緊急立法として借地人の保護が一層強化されました。この改正により、借地期間が満了しても地主が正当事由なしに更新を拒絶できない制度が確立され、借地人の権利が半永久的に保護されるようになりました。
旧法は1992年まで71年間にわたって運用されましたが、時代の変化に伴い地主の権利が著しく制限される問題が顕在化しました。土地の流動性が低下し、有効利用が阻害される状況が続いたため、新法への改正が必要となったのです。
借地借家法と旧法借地法の主な違い
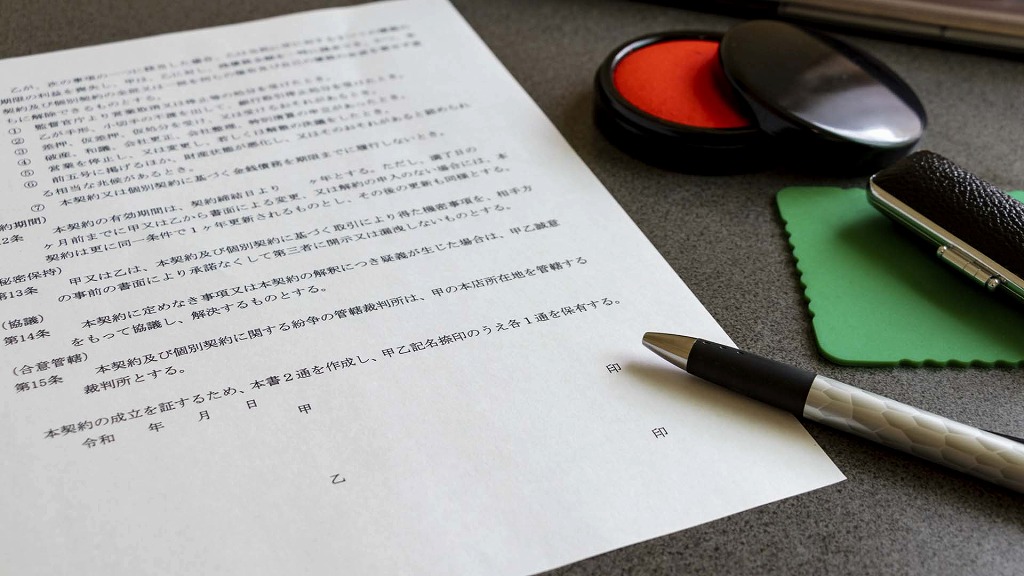
現行法では定期借地権制度が導入され、土地の返還が格段に容易になりました。旧法では普通借地権のみが存在し、地主が土地を取り戻すことは極めて困難でした。
存続期間について、旧法では建物の構造により異なる期間が設定されていました。堅固な建物(鉄筋コンクリート造等)は60年、非堅固な建物(木造等)は30年とされていました。一方、現行法では建物の構造に関わらず一律30年となり、契約関係が簡素化されました。
更新制度にも大きな変化があります。旧法では借地人の権利が強く、地主が正当事由を証明することは非常に困難でした。現行法では、地主の権利も適切に保護され、一定の条件下で更新拒絶が可能となっています。
2025年の地価公示では、全国の全用途平均で4年連続上昇し、上昇幅が拡大している状況下で、土地の有効利用を促進する新法の意義はより高まっています。
新旧ふたつの法律を比べると?

借地借家法では、借地権の種類が大幅に拡充されました。普通借地権に加えて、一般定期借地権(50年以上)、建物譲渡特約付借地権(30年以上)、事業用定期借地権(10年以上50年未満)が新設され、契約の自由度が格段に向上しました。
判例においても、新法の施行により解釈が明確化されています。昭和57年2月4日の重要判例では、借地権の存続期間に関する解釈が示され、法的安定性が向上しました。現行法では、このように過去の判例の蓄積を踏まえ、より一貫性のある法適用が可能となっています。
2022年5月の改正では、一般定期借地権の特約が電磁的記録でも可能となり、契約手続きの利便性が大幅に向上しました。これにより、従来の公正証書による契約に加え、電子契約での締結が可能となり、取引コストの削減が実現されています。
地価上昇局面での法運用上の課題
不動産市場の変化に対応した法運用が重要な課題となっています。2025年の公示地価は全国平均で+2.7%となり、前年を上回る上昇率を記録する中で、土地の有効利用がより一層求められています。
相続を控えた地主にとって、借地権の更新や解約に関する複雑な手続きは大きな負担となります。特に、旧法適用の借地契約については、更新時にも旧法が適用されるため、現在でも多くの借地が旧法の規制下にあります。
現代の不動産投資においても、借地権の種類や契約条件の複雑化により、専門知識が必要な場面が増加しています。定期借地権は投資家に一定期間の収益を保証する一方で、契約終了後の不確実性が投資リスクとして認識されています。
法改正による市場への影響
2022年5月の改正により、定期建物賃貸借に係る事前説明書面の交付等が電磁的方法でも可能となり、不動産取引の効率化が進んでいます。これにより、手続きの簡素化と取引コストの削減が実現し、市場の活性化に寄与しています。
電子契約の導入は、特に遠隔地の取引や複数当事者間の契約において大きなメリットをもたらしています。従来の紙ベースの契約では時間とコストがかかっていた手続きが、オンラインで完結できるようになりました。
地主と借地人の権利バランスの改善により、土地の供給が増加し、市場の流動性が向上しています。定期借地権の活用により、これまで貸し出しを控えていた地主も、期間限定で土地を提供するケースが増えています。
相続・売却における実務上の留意点
相続時には借地権の種類により対応が大きく異なります。旧法適用の借地権は更新が容易で資産価値が高い反面、相続税評価も高額になる傾向があります。現行法の定期借地権は、契約期間の満了により土地が返還されるため、相続対策として活用されることがあります。
売却を検討する際は、借地権の種類と残存期間の確認が必要です。旧法借地権は更新が前提となっているため、購入者にとって魅力的な投資対象となりますが、現行法の定期借地権は契約期間に応じて価値が変動します。
2025年の地価公示では、全国25,519地点で調査され平均金額は275,693円/m²となっており、借地権の評価においても最新の地価動向を反映した査定が重要です。
今後の展望と対策

不動産市場の健全な発展には、借地借家法の継続的な見直しが必要です。特に、都市部での土地不足と地方での空き地問題という二極化現象への対応が求められています。
デジタル技術の進歩により、契約手続きの電子化は今後さらに進展すると予想されます。ブロックチェーン技術を活用した契約管理や、AI による契約条件の自動判定なども検討されています。
地主・借地人双方にとって公平で透明性の高い制度構築により、土地の有効活用と不動産市場の活性化が期待されています。
借地権の売却や相続でお悩みの方は、専門家による適切な査定を受けることが重要です。法律の複雑な仕組みを理解し、最適な売却戦略を立てるためには、経験豊富な不動産会社との相談が欠かせません。クラシエステート株式会社では、旧法・現行法の両方に精通した専門スタッフが、お客様の状況に応じた最適なソリューションを提供いたします。
まずは無料査定で、お持ちの借地権の現在価値を正確に把握してみませんか。
無料不動産価格査定|クラシエステート株式会社
参考文献
- 法務省「借地借家法等の改正(定期借地権・定期建物賃貸借関係)について」
- 国土交通省「令和7年地価公示」
- デジタル庁「借地借家法の改正について」
- One Asia Lawyers「日本における改正借地借家法の概要について」(2022)
- 地価マップ「2025年地価公示・地価調査」
