借地権設定登記不可の状況でも、借地権を保護する方法はあります。
地主の協力が得られない場合でも、建物登記という代替手段を使えば、第三者に対して借地権の存在を主張できるのです。
その理由や背景、ノウハウを知るため、この記事では以下のポイントについて解説しました。
- 借地権設定登記ができない理由と対処法
- 建物登記による対抗要件の確保方法
- 相続や譲渡時の注意点とリスク回避策
- 専門家への相談が必要なケースの見極め方
借地権設定登記ができない理由とその背景

借地権も土地登記簿に登載できる事項です。当然、登記できれば最も確実に権利を守ることができるのですが、現実的には、借地権の登記を見かけることはめったにありません。
その理由を知り、対策方法を考えていきましょう。
地主の協力が得られないという現実的な問題
借地権設定登記ができない最大の原因は、地主の協力が得られないことです。法律上は借地権が有効に成立していても、登記手続きには地主と借地人の共同申請が必要なため、地主が協力してくれないと登記は進められません。
地主が協力を拒む理由には、登記による権利関係の明確化を嫌がる心理や、将来的に土地利用の制約を受けたくない気持ちがあります。また、登記費用の負担や手続きの煩雑さを避けたいという現実的な理由もあるでしょう。
このように地主はなかなか協力してくれないわけですから、借地人は別の方法で自分の権利を守る必要があります。
借地権設定登記に関して、まずは地主と話し合うことが大切です。それでも協力が得られない場合は、借地借家法に認められた手段を使って権利を守ることになります。
その「手段」とは、借地上に建てた建物を自分の名義で登記することなのです。
建物登記による第三者対抗要件を備える方法

借地借家法は、借地人が、その土地上に所有する建物を自己名義で登記することで第三者に対抗できると定めています。
借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。--借地借家法第10条1項
しかも、借地上の建物が滅失しても、滅失前の建物を登記しており、かつ借地権者が「その建物を特定するために必要な事項」「滅失があった日」「建物を新たに築造する旨」を土地上の見やすい場所に掲示すれば、滅失の日から2年間は借地権の対抗力が維持されるとも規定されています。
つまり建物を登記しておくことで、ある程度安心できるといえるでしょう。
ステップ1:建物の建築と登記準備
借地権設定登記不可の場合の最も有効な対処法は、借地上に建物を建築し、その建物を自分の名義で登記することです。直接的な保護手段がなくても、間接的に類似の効果を得られる……と考えるといいでしょう。
建物登記による対抗要件の確保には、まず適切な建物の建築が必要です。この建物は借地権者が地震が所有し、登記可能な構造である必要があります。
仮設的な建物や登記要件を満たさない簡易な構造物では、十分な対抗力を得られません。
登記申請手続きは、一般的に土地家屋調査士さんに依頼します。
ステップ2:借地権者名義での建物登記実行
建物が完成したら、借地権者の名義で建物登記を行います。この登記により、第三者が建物の存在と所有者を確認でき、同時に借地権の存在も推測できるようになります。建物登記は借地権の存在を間接的に公示する効果があるといえるでしょう。
登記申請によって、建物の所有者が借地権者であることを示し、土地の利用目的が建物所有であることを証明できます。これは土地が第三者に譲渡された場合でも、新しい所有者に対して借地権を主張する根拠となります。
建物登記の際は、登記簿に記載される情報が正確であることを確認し、必要書類を抜け漏れなく準備してください。
ステップ3:対抗力の維持と管理
建物登記が完了した後も、その対抗力を維持するための管理は怠れません。建物の維持管理を怠ると、実質的な建物所有の事実が失われ、借地権の対抗力が認められにくくなる可能性があります。
建物の登記事項に変更が生じた場合は、速やかに変更登記を行い、登記簿の内容を最新の状態に保つことも重要です。また、建物の増改築や用途変更があった場合も、適切な登記手続きを行う必要があります。
相続・譲渡時の注意点とリスク回避策

相続や譲渡で、借地権付きの不動産(建物)の所有者が変わることがあります。このタイミングで地主と揉めやすく、所有権移転については慎重に進めた方がいいでしょう。
相続と譲渡(売却など)の場合に分けて考えてみましょう。
相続時の権利継承における課題
借地権を相続する際も注意が必要です。相続は親から子へと財産を引き継ぐ自然な流れですが、登記のない借地権の場合、その権利の存在を証明することが難しい場合があります。
相続人は被相続人の地位を承継しますが、第三者に対する対抗力は建物登記に依存することになります。このため、相続発生後は速やかに建物の所有権移転登記を行い、新しい所有者であることを明確に示す必要があります。
また、相続税の申告においても借地権の評価が必要になります。この点は、税理士などに相談するのがいいでしょう。不動産会社で、こういった問題に強い税理士を紹介してくれることもありますので、まずは尋ねてみるのがいいでしょう。
譲渡時の地主承諾と手続き
借地権の譲渡には地主の承諾が必要です。不動産譲渡である点では、家を売るのと似ていますが、借地権の場合は土地の所有者である地主の同意が不可欠な点が異なります。
地主の承諾を得る際は、譲受人の信用状況や建物の利用計画などを説明し、地主が安心できる条件を提示することが重要です。また、承諾料の支払いが求められる場合もあるため、事前に交渉しておく必要があります。
譲渡契約書には借地権の内容を明確に記載し、建物登記による対抗力についても適切に説明することが大切です。これにより、譲受人が将来的に不利益を被ることを防げます。
敷金・保証金の承継問題
借地権の譲渡に伴い、敷金や保証金の承継についても整理が必要です。これらの金銭は借地契約に付随する重要な要素であり、放置しておくと後々トラブルの原因となります。
敷金の返還請求権は原則として新しい借地権者に移転しますが、地主との間で明確な合意を取得しておくほうが安全です。また、保証金についても同様に、承継の条件を明確にしておく必要があります。
かなり複雑な書類作成を行う必要があることから、司法書士や弁護士などの専門家に依頼するのが確実でしょう。
法的リスクと対処方法

借地権は強力な権利ではありますが、法的には一定のリスクもあります。
ここでは、抑えておきたい法的リスクを解説します。
民法177条の例外適用による保護
借地権設定登記ができない場合でも、民法177条の例外により保護される可能性があります。
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。-- 民法177条
この条文は不動産の権利変動について登記を対抗要件とする原則を定めていますが、すべての第三者が保護されるわけではありません。
背信的悪意者と呼ばれる、借地権の存在を知りながら不正な手段で土地を取得した者に対しては、登記がなくても借地権を主張できる場合があります。これは正義に反する行為を法律が許さないという考え方に基づいています。
ただし、この例外適用には要件があり、単に借地権の存在を知っていただけでは不十分です。具体的な事実関係に基づいて判断されるため、詳しくは法律家の判断を聞いたほうがいいでしょう。
登記制度の変化と対応策
近年、相続登記の義務化など登記制度に関する法改正が進んでいます。こういった制度面の変化が借地権にも影響を与える可能性があります。
たとえば、2024年4月から相続登記が義務化され、相続人は相続を知った時から3年以内に登記申請を行うことが義務づけられました。この法改正によって、建物登記についても相続時の手続きがより重要になっています。
また、デジタル化の進展により、登記手続きの電子化も進んでいます。これらの変化に対応するためには、最新の情報を把握し、適切な手続きを行うことが重要です。
プロに相談することも大切
借地権は全般に、法的な専門知識を必要とする複雑な分野です。その意味で、プロの意見が重要なジャンルともいえるでしょう。
司法書士は登記手続きの専門家として、建物登記による対抗要件備えるなどの対策が可能です。また、弁護士は地主との交渉や法的トラブルの解決において重要な役割を果たします。税理士は相続税や譲渡所得税などの税務面での支援を提供します。
こういった士業の専門家との連携により、借地権設定登記不可という状況でも適切な権利保護を実現できます。費用はかかりますが、将来的なリスクを考慮すれば、必要な投資といえるでしょう。
借地権と登記についてのよくある質問(Q&A)
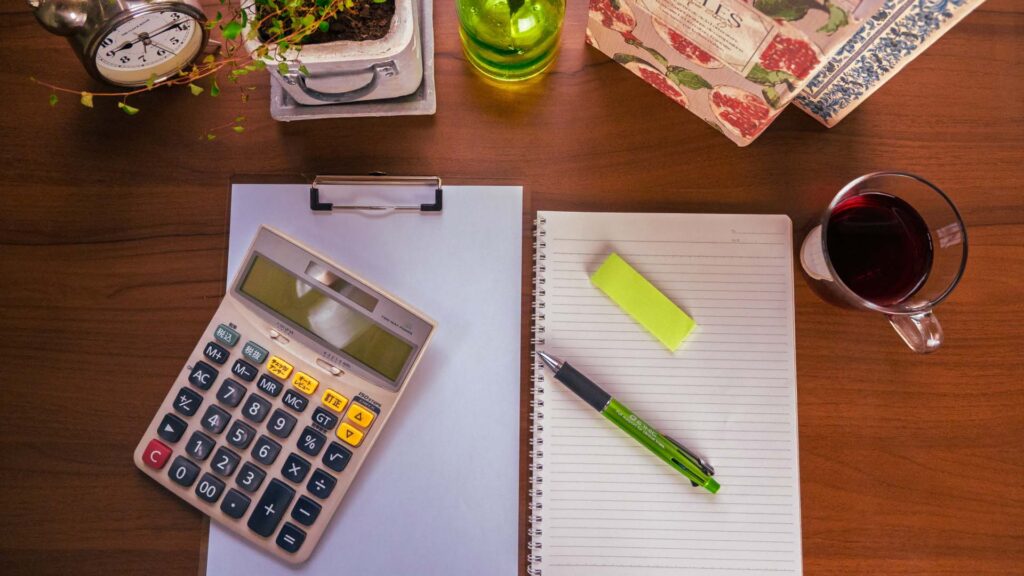
最後に、本文で触れた重要論点と、触れられなかったポイントをQ&A形式にまとめました。
借地権設定登記不可の場合、建物登記以外に対抗要件を確保する方法はありますか?
建物登記が最も確実で一般的な方法ですが、他にも一定の手段・対策があります。例えば、地主が背信的悪意者である場合や、物理的に権利の存在が明示されている場合には、民法177条の例外として登記なしでも対抗できる可能性があります。ただし、これらの例外適用には厳格な要件があり、具体的な事実関係に基づいて判断されるため、弁護士等による判断が不可欠です。実務的には建物登記による対抗要件の確保が最も安全で確実な方法といえるでしょう。
建物登記による対抗要件はどの程度の効力がありますか?
建物登記による対抗要件は、借地権設定登記が不可の場合においては強力な効力を持ちます。建物が適切に登記されていれば、土地が第三者に譲渡された場合でも、新しい所有者に対して借地権の存在を主張できます。これは建物の存在により借地権の利用実態が明確になり、第三者も借地権の存在を認識できるためです。ただし、建物の維持管理を怠ったり、実質的な利用実態がなくなったりすると、対抗力が弱くなる可能性があるため、継続的な管理が重要になります。
相続時に建物登記の名義変更を怠った場合のリスクは何ですか?
相続時に建物登記の名義変更を怠ると、借地権の対抗要件が不安定になる重大なリスクがあります。登記簿上の所有者が被相続人のままだと、第三者から見て現在の権利者が不明確になり、借地権の存在を主張する根拠が弱くなります。また、2024年4月からは相続登記が義務化されており、相続を知った時から3年以内に登記申請を行わないと過料の対象となります。さらに、名義変更を怠っている間に他の相続人が権利を主張したり、第三者との間でトラブルが発生したりする可能性もあるため、早め早めの手続きが必要です。
地主の承諾が得られない場合の借地権譲渡について教えてください。
地主の承諾が得られない場合でも、借地権の譲渡を実現する方法があります。借地借家法では、地主が承諾を拒否する正当な理由がない場合、家庭裁判所に承諾に代わる許可を求めることができます。この手続きでは、譲受人の信用状況や借地権の利用計画などを考慮して、裁判所が承諾の可否を判断します。ただし、法的手続きには時間と費用がかかるため、まずは地主との話し合いによる解決を試みることが重要です。承諾料の支払いや利用条件の調整により、地主の理解を得られる場合も多いため、専門家のアドバイスを受けながら適切な交渉を進めることをお勧めします。
まとめ

借地権設定登記不可の状況でも、建物登記による対抗要件の確保により、あなたの借地権は適切に保護できます。地主の協力が得られない場合でも諦めず、法的に認められた代替手段を活用することが重要です。
相続や譲渡の際は特に注意が必要であり、専門家への相談により安全な手続きを進めることができます。最新の法改正にも対応しながら、確実な権利保護を実現しましょう。
借地権でお困りの方は、ぜひクラシエステート株式会社の専門スタッフにご相談ください。あなたの状況に応じた最適な解決策をご提案します。
お問い合わせフォーム|クラシエステート株式会社
